交通事故の休業損害|いつまでの期間もらえるか?
最終更新日:2025年03月13日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q交通事故の休業損害はいつまでの期間もらえますか?
-
休業損害がもらえる期間は、けがのために仕事を休む必要がある期間です。具体的には、医師の診断により仕事を休む必要があると判断された日から、けがが完治する、または症状が固定するまでの期間です。
もっとも、けがや休業の状況により休業損害をもらえる期間は異なります。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。


1. けがや治療で休めば休業損害が支払われる可能性
交通事故でけがをすると、仕事を休まざるを得ないことがあります。
たとえば、入院していて会社に行けない、痛くて仕事ができない、通院のために休まなければならない場合です。その結果、収入が減ってしまうケースも少なくありません。こうした休業による収入の減少を賠償するのが「休業損害」です。
休業損害は、交通事故がなければ発生しなかった損害で、事故の加害者に請求できます。
ただし、すべてのケースで必ず支払われるわけではなく、休業の必要性や期間を証明することが必要です。
最大で事故発生から症状固定時まで支払い
休業損害が支払われる期間の始まりは、交通事故が発生した日からです。事故でけがをして仕事を休んだ場合、その日から賠償の対象になります。
一方、支払いの終わりは、けがが治るか、症状固定日までです。症状固定とは治療を継続しても効果が見込まれず、症状の改善がない状態のことです。
治療が必要な間は仕事を休むこともやむをえないと考えられるため、その期間の休業損害が賠償されます。
現実的には事故発生から症状固定時までの一部で支払い
理論上は事故が発生してから症状が固定するまでが休業損害の対象ですが、実際にはそのすべてが認められるわけではありません。
たとえば、次のようなケースでは休業損害が減らされたり、途中で支払いが止まったりすることがあります。
- 医師から仕事を再開できると言われた場合
- けがの内容や症状、事故の衝撃から仕事ができると判断される場合
- 自己判断で通院をやめてしまった場合
- 仕事を休んだ理由が治療とは関係ないと判断された場合
休業損害を適正に受け取るためには、医師の指示に従い治療を続けることが大切です。途中で治療をやめると、その時点で休業損害の支払いが打ち切られることがあるため注意しましょう。
休業損害と慰謝料の違い
休業損害と慰謝料は、どちらも交通事故の被害者が請求できるものですが、賠償の目的が異なります。
休業損害は、事故の影響で仕事ができなかった期間の収入減を補填するものです。交通事故が発生し、治療などのために仕事を休んだ日が対象となり、基本的には完治または症状固定までの間が支払いの対象となります。治療期間が長引くほど請求できる期間も延びますが、休業の必要性が認められなければ対象外となることもあります。
一方、慰謝料は、交通事故による精神的な苦痛に対する賠償です。収入の有無には関係なく、けがの程度や治療期間を基に計算します。治療が長引けば慰謝料の額も増える傾向にありますが、一定の基準に基づいて決められるため、休業損害のような直接的な収入の補填とは異なります。
打撲や捻挫で仕事を休まないで通院し、休業損害は請求せず、慰謝料のみ請求するようなケースもたくさんあります。
休業損害と休業補償の違い
休業損害と休業補償は、名称が似ていますが、支払いの条件が異なります。
休業補償は、仕事中の事故や業務が原因でけがを負って仕事を休んだ場合に、労災保険から支給されるものです。交通事故であっても、通勤中や業務中に発生した事故であれば、労災保険の対象となることがあります。
一方休業損害は、交通事故が原因で仕事を休んだ場合に発生し、加害者に対して請求するものです。支払われる期間は、事故日から完治または症状固定までの間で、実際に仕事を休んだ日数が基準となります。
休業補償は国、休業損害は保険会社と請求先が異なるため、支払いの条件や、休業の必要性の判断も異なることがあります。どちらにどのように請求するのか検討することが重要です。
休業損害と逸失利益の違い
休業損害と逸失利益は、どちらも事故による収入の減少を賠償するものですが、対象となる期間が異なります。
逸失利益は、後遺症が残った場合に将来の収入が減ることを賠償するものです。症状固定後、以前のように働くことが難しくなった場合、将来の収入減を見越して支払われます。事故によってどの程度労働能力が低下したのかを判断するため、長期間の収入減を賠償する制度といえます。
一方休業損害は、事故発生から完治または症状固定までの間に仕事を休んだことで生じた収入の減少を補填するものです。治療が必要な期間に仕事を休んだ日数が補償の基準となるため、比較的短期間の損害に対応する賠償といえます。
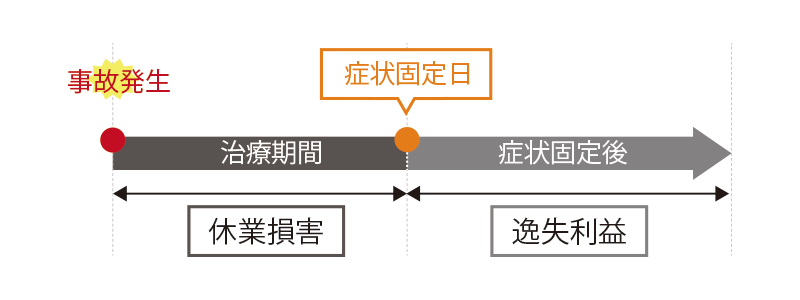
損害賠償金は非課税
交通事故の損害賠償金は、基本的に課税対象にはなりません。これは、事故によって被った損害を補填するためのものであり、新たな所得とはみなされないためです。
ただし、一部例外がある可能性もあります。
事故による損害賠償金の扱いについて不安がある場合は、税理士などの専門家に相談するのが安心です。
2. 会社員・アルバイトなどの給与所得者
会社員やアルバイトの場合、休業損害は事故前の給与を基準に計算します。
休業期間が長くなるほど損害額も大きくなりますが、長期間の休業が必要と認められるには医師の診断や会社の休業証明が必要です。
【計算方法】
事故前3か月間の給与をもとに1日あたりの収入を求め、休業日数を掛けて算出します。
【計算式】
休業損害=(事故前3か月の給与合計÷勤務日数)×休業日数
休業期間は、医師の診断で就業が難しいと認められた日数が基本となります。
3. 自営業者・個人事業主・フリーランス
自営業者やフリーランスは、給与所得者とは異なり「所得」を基に休業損害が算出されます。特に、長期間の休業が続く場合は、事業継続にかかる固定費の補償も考慮されることがあります。
【計算方法】
前年の確定申告の所得をもとに1日あたりの収入を算出し、休業日数を掛けて求めます。
【計算式】
休業損害=(前年の申告所得÷365日)×休業日数
休業が長期化する場合、事故がなければ継続的に収入を得られていたことを証明するため、売上帳や契約書の提出が必要になることもあります。
休業期間は、医師の診断で就業が難しいと認められた日数が基本となります。
ただし、会社員と違い、第三者の休業証明が得にくいため、被害者自身で休業日数・時間を記録したり、売り上げの減少を証明する必要があるケースもあります。
4. 会社役員
会社役員の休業損害は、役員報酬のうち「労働対価」としての部分のみが補償対象となります。役員報酬には利益配当も含まれるため、すべてが休業損害の対象にはなりません。
【計算方法】
年間の役員報酬のうち労働対価部分を基準に1日あたりの収入を求め、休業日数を掛けて算出します。
【計算式】
休業損害=(役員報酬年収-利益配当分)÷365日×休業日数
会社役員の場合、保険会社が休業損害自体を否定することも多いです。また、休業期間が長期に及ぶと、役員報酬の減額など特別の事情がない限り、休業損害が一層認められにくくなります。そのため、休業損害の請求をする場合は、実際に減収があったことを示す資料があれば、これを示すことが重要です。
休業期間は、医師の診断で就業が難しいと認められた日数が基本となります。
5. 専業主婦・兼業主婦などの家事従事者
家事労働も経済的な価値があるため、休業損害を請求できます。家事ができない期間が長くなるほど損害額も増えますが、完全に家事を行えなかった期間を証明することが重要です。
【計算方法】
賃金センサスに基づく女性の全年齢平均賃金を基準とし、1日あたりの基礎収入を算出して休業日数を掛けます。
賃金センサスとは、厚生労働省が毎年発表する「賃金構造基本統計調査」のデータで、年齢・性別・学歴・職種ごとの平均賃金を示したものです。
【計算式】
休業損害=(賃金センサスの女性平均年収÷365日)×休業日数
休業期間が長引く場合、医師の診断書や家事ができないことを示す証拠(家事代行の領収書など)が必要になることがあります。
家事は毎日行うものなので、半分程度できなかった、4分の1程度できなかったなど、割合的に休業日数を計算することもあります。
休業期間や休業日数は、個別具体的な事案によって異なります。判断に迷ったときは弁護士への相談をおすすめします。

6. 休業損害の期間の交渉のポイント
休業損害の期間は、①事故による仕事への影響の程度や②けがの回復状況に左右されます。
納得できる休業損害をもらうには、次のポイントを押さえることが重要です。
休業している証拠をそろえて請求する
休業損害を請求するには、実際に仕事を休んでいたことを証明する書類が必要です。事故により就業が困難になったことを証明できないと、保険会社が休業損害の支払いを渋ることもあります。そのため、職業ごとに適切な証拠を準備することが重要です。
会社員やアルバイトの場合、休業損害証明書を勤務先から発行してもらいましょう。これは、事故後に何日間仕事を休んだのかを証明するための書類で、保険会社が休業日数を認める根拠となります。また、事故前の給与明細や源泉徴収票を提出することで、事故がなければ得られたはずの収入を示すことができます。
自営業者やフリーランスの場合は、売上帳や確定申告書、銀行の入出金記録、取引先との契約書などを用意します。特に、事故前後で売上に変化がある場合、それを証明する書類を整えることで休業による損害をより明確に伝えることができます。被害者自身で休業日数や時間をメモしたり記録したりすることも選択肢の1つです。
専業主婦の場合は、家事ができなかったことを示すための証拠を準備しましょう。たとえば、家事代行サービスの領収書、家族の協力を得た記録、または家族の証言などが有効です。休業損害の期間が長くなるほど、証拠の有無が賠償額に影響を与えるため、できるだけ客観的な資料を準備しましょう。
休業損害を適正に受け取るためには、仕事を休んでいたことが分かる証拠をしっかりと準備し、保険会社に提出することが重要です。
けがが原因で就労不能という証拠をそろえて請求する
休業損害を請求するためには、事故による負傷の影響で働けなかったことを証明する必要があります。ただ仕事を休んでいただけでは、保険会社は休業損害の支払いを認めないことがあるため、医師の診断書や通院記録などの証拠を用意しましょう。
まず、医師の診断書の有無は重要です。診断書には、受傷した部位、症状の程度、治療の必要性、そして仕事ができるかどうかの判断を記載してもらいましょう。保険会社は、医師が休業を指示していると認めれば、休業損害を認める傾向があります。
次に、通院の記録やリハビリの計画書も重要な証拠となります。リハビリ計画書にはリハビリの内容や、リハビリの目標が書いてあるため、就労不能であることを示す証拠になります。通院回数が少ない場合、保険会社から「仕事を休むほどのけがではなかったのではないか」と指摘されることがあります。定期的に医療機関を受診し、治療を継続していることを示すことで、休業の必要性を証明できます。
また、会社員の場合は、勤務先から「けがによる就業制限」の証明書をもらうのも有効です。たとえば、重い物を持つ作業ができない、長時間のデスクワークが難しいなど、事故による支障があることを勤務先が認めていれば、保険会社も休業損害の支払いを認めやすくなります。
自営業者やフリーランスの場合は、通常の業務ができなかったことを示すための証拠を準備しましょう。たとえば、事故後に予定していた仕事がキャンセルになったことを示すメールの履歴、業務が継続できず収入が減少したことを証明する売上帳や取引先とのやり取りの記録などが有効です。
このように、単に仕事を休んだことだけでなく、事故によるけがが原因で休業が必要だったことを証明することが、適正な休業損害をもらうことにつながります。
納得できなければ弁護士に相談する
休業損害を請求しても、保険会社が提示する金額が少なすぎる、あるいは支払い自体を認めないことがあります。
特に、休業期間が長引くと「本当に仕事ができなかったのか」と疑われ、途中で支払いを打ち切られるケースもあります。
また、保険会社が休業日数を実際より短く見積もることもあります。例えば、医師が「最低1か月の休業が必要」と診断しているのに、保険会社が「2週間しか認められない」と主張するケースです。
このような場合、弁護士が医師の診断書や勤務先の証明書をもとに交渉し、実際に必要な期間の賠償を求めることができます。
休業損害に関するトラブルは、専門的な知識がないと適切に対処するのが難しいことがあります。保険会社の対応に納得できない場合は、弁護士に相談し、正当な補償を受けるための手続きを進めることが重要です。
7. まとめ:休業損害の期間の計算方法
休業損害は、事故発生日から完治または症状固定までの期間が対象となりえます。ただし、実際の期間は医師の診断や保険会社の判断によって変わります。
治療中は、診断書や通院記録が休業の必要性を証明する重要な証拠になります。医師の指示に従い、治療を続けることが大切です。
また、会社員やアルバイトは休業損害証明書を準備しましょう。自営業者やフリーランスは、売上の減少や仕事ができなかったことがわかる書類を準備しましょう。
期間について保険会社と意見が合わない場合は、弁護士に相談することも1つの選択肢です。納得できないときは、まずは弁護士に相談してみましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博















