交通事故の被害者向け|刑事手続きの流れ
最終更新日:2025年04月10日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q【被害者向け】交通事故の刑事手続きの流れはどのようなものですか?
-
交通事故が発生すると、警察が現場検証を行い、加害者の取り調べが始まります。事故の状況や被害の大きさによっては、加害者が逮捕されることもあります。その後、検察官が起訴するかどうかを判断し、起訴されれば刑事裁判へと進みます。
交通事故の刑事手続きの流れは複雑です。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。

目次

交通事故の刑事手続きの流れ全般
交通事故の刑事手続きは、次の流れで進みます。
- 警察の対応
- 検察の判断(起訴・不起訴)
- 刑事裁判(起訴の場合)
-
警察の対応
事故が発生すると、警察が現場で事故の状況を確認し、加害者・被害者から事情聴取をします。事故の重大性に応じて、加害者の取り調べや実況見分が行われます。悪質なケースでは、加害者が逮捕されることもあります。
-
検察の判断(起訴・不起訴)
取り調べが終わると、検察官が「起訴するかどうか」を判断します。加害者が示談を成立させ、被害者が処罰を望まない意思を示せば、不起訴処分となり、裁判にならずに事件が終了する可能性もあります。
しかし、悪質な事故や過失の大きい事故では、示談が成立しても起訴される場合があります。
-
刑事裁判(起訴された場合)
起訴されると、刑事裁判が行われ、加害者に刑罰が科されるかどうかが決まります。
裁判には、略式裁判と正式裁判の2種類があり、罰金刑が科される場合は略式裁判となることが多いです。正式裁判では、被害者の供述や証拠をもとに、加害者の責任がどの程度あるのかが審理され、有罪であれば懲役や罰金が科されることになります。
事故当日や直後の警察とのやりとり

交通事故にあった直後は、気が動転してしまうものですが、警察への対応が今後の示談交渉や損害賠償請求に大きく影響します。ここでは、事故直後に警察と被害者がどのようなやり取りをするのかを解説します。
-
警察への通報
交通事故が発生したら、まずは110番通報を行います。加害者が「警察を呼ばずに示談にしたい」と言ってきても、応じてはいけません。事故の届出をしないと保険の請求ができなくなる可能性があるため、必ず警察を呼びましょう。
通報時に伝える内容は次の通りです。
- 事故の発生場所(住所や目印になる建物・交差点)
- 事故の状況(車同士の衝突・歩行者事故など)
- 負傷者の有無(救急車が必要かどうか)
- 加害者が現場にいるかどうか
-
警察が現場に到着した後のやりとり
警察が現場に到着すると、事故の詳細を確認し、加害者・被害者双方から事情を聞き取ります。被害者は、事故の状況をできる限り正確に伝えることが重要です。
事故の状況を説明する際、無理に詳細を作り込まず、分かる範囲で正確に伝えることが大切です。記憶が曖昧な部分は「分からない」と伝え、加害者側の主張に惑わされないようにしましょう。
-
警察への届け出
警察が事故処理を行う際、「人身事故」か「物損事故」かの分類を決めます。加害者が「物損事故扱いにしてほしい」と頼んでくることがありますが、安易に応じてはいけません。
「物損事故」として処理されると、加害者に対する刑事処分が軽くなり、保険会社の対応も変わる可能性があります。また、後からけがが悪化して人身事故として届け出ようとしても、警察に認めてもらえない場合があります。けがをしている場合は「人身事故」として処理してもらうのがおすすめです。
実況見分調書や供述調書

実況見分調書と供述調書は、交通事故の責任を明確にするための重要な書類です。実況見分では警察が現場の状況を記録し、供述調書では加害者や被害者の証言がまとめられます。
実況見分調書の作成(警察)
実況見分調書とは、警察官が事故現場で行う実況見分の結果を記録した書類です。交通事故の発生状況を客観的に記録するものであり、事故原因や過失割合を判断する重要な証拠になります。
実況見分は、次のように進められます。
① 事故現場の確認
警察官が事故現場に到着すると、まずは事故の状況を詳しく調査します。事故当時の状況をできる限り正確に再現することが目的です。
被害者としても、可能であれば事故現場の写真を自分で撮影しておくと、後の証拠として役立ちます。
② 加害者・被害者の説明を聞く
警察官は、加害者と被害者の両方から事故状況についての説明を聞きます。
被害者としては、記憶が曖昧な部分を無理に作り込む必要はありません。「分からないことは分からない」と伝えた方が、後で証言に矛盾が生じるリスクを避けられます。
③ 事故現場の写真撮影と見取り図の作成
警察は、事故現場の状況を記録するために写真撮影や見取り図の作成を行います。
見取り図の作成の際には、加害者を立ち会わせて、速度や被害者の確認状況、進路変更を開始したタイミング等について詳細な聞き取りをすることが多いです。
これらの資料は、加害者の過失を立証するための重要な証拠になります。
④ 実況見分調書の作成
当事者の説明や警察官が現場を確認した情報をもとに、警察が「実況見分調書」を作成します。
実況見分調書は通常立会人の指示説明、見取り図、事故現場の写真が一体になっています。
供述調書の作成(警察や検察)
供述調書とは、加害者や被害者の証言を記録した書類で、警察や検察が取り調べの際に作成します。供述調書は、事故の責任を判断する重要な証拠となり、加害者の刑事処分や民事の示談交渉に影響を与えることがあります。
供述調書は、次の流れで作成されます。
① 警察の取り調べ
警察官は、事故がどのように発生したのかを確認するため、加害者や被害者に対して詳しく事情を聞きます。主に、事故が起こった時の状況について説明を求められます。
警察の取り調べでは、できる限り記憶に基づいて正確に話すことが大切です。事故の詳細を正確に伝えることで、加害者の責任を適切に追及できる可能性が高まります。
しかし、事故のショックで記憶が曖昧な部分もあるかもしれません。そのような場合、無理に話を作るのではなく、「覚えていません」と正直に伝えることが重要です。間違った情報を伝えてしまうと、加害者に有利な供述として記録される可能性があります。
警察の取り調べでは、冷静に自分が知っている事実を正確に伝え、曖昧な部分については無理に推測で答えないようにしましょう。
② 検察の取り調べ(必要な場合)
事故が重大な場合や過失が大きいと判断された場合、検察官が直接、被害者や加害者の供述を確認します。検察官は、警察の調書やこの取り調べで得た供述をもとに、加害者を起訴するかどうかの判断を行います。
もし加害者の厳正な処罰を望むのであれば、その意思を明確に伝えることが大切です。具体的には、加害者が誠意をもって謝罪していない、示談交渉が難航している、事故による精神的・肉体的な影響が大きいといった事情を、できるだけ詳細に説明しましょう。特に当初の見込みより治療が長引いている、後遺障害が残った等の場合はそのことを伝えましょう。
検察官は、被害者の意見や感情を考慮しつつ、法律に基づいて起訴の判断を行います。そのため、処罰を求める場合は「厳正な処罰を望みます」とはっきり伝え、被害の実態や加害者の対応をしっかりと説明することが重要です。
③ 供述調書の作成
検察官や警察官の取り調べが終わると、その内容をもとに供述調書が作成されます。供述調書には、被害者が供述した事故の状況や、加害者に対する意見、被害の程度などが記録されます。これは、刑事手続きの中で重要な証拠となるため、慎重に内容を確認することが必要です。
供述調書が作成された後、警察官または検察官から内容が読み上げられ、被害者が確認を行います。ここで、自分の証言と異なる部分があれば、遠慮せず訂正を求めましょう。「多少の違いだから」と思って訂正しないと、後の手続きで加害者に有利に働く可能性があります。特に具体的な速度の記載はその後の民事手続きでも過失割合に影響を与えやすいです。
一度署名・押印すると、後から内容を訂正することは非常に難しくなるため、細かい部分まで慎重に確認することが重要です。
また、供述調書には、事故による被害の大きさや、被害者の処罰感情が記録されることもあります。事故後の精神的な苦痛や生活への影響についてもしっかり伝え、それが適切に記載されているか確認しましょう。供述調書は、被害者の声を公的に残す大切な記録です。そのため、納得のいく形で署名・押印することを心がけましょう。
起訴・不起訴の結果を確認
交通事故の加害者が刑事責任を問われるかどうかは、最終的に検察官が決定します。検察官は警察から送致された事件を精査し、起訴(裁判にかける)するか、不起訴(裁判をしない)とするかを判断します。被害者としては、加害者がどのような処分を受けるのかを知ることが重要です。
起訴・不起訴の結果は、主に次の方法で確認できます。
-
捜査機関からの通知を受け取る
被害者が警察や検察に対して「被害届」や「告訴状」を提出している場合、検察官は事件の処分結果を被害者に通知することが一般的です。
また、「被害者連絡制度」「被害者等通知制度」を利用すると、事件の進行状況や最終的な処分について詳しく知ることができます。これにより、「起訴された」「不起訴になった」「裁判が開始された」などの情報を受け取ることができます。
-
検察庁に問い合わせる
事件が検察庁に送致された後、被害者は担当の検察官に問い合わせることで、起訴・不起訴の結果を確認できます。
問い合わせ先は、事件を担当した地方検察庁になります。事件番号や被害届を出した日時を伝えると、スムーズに回答を得られることが多いです。
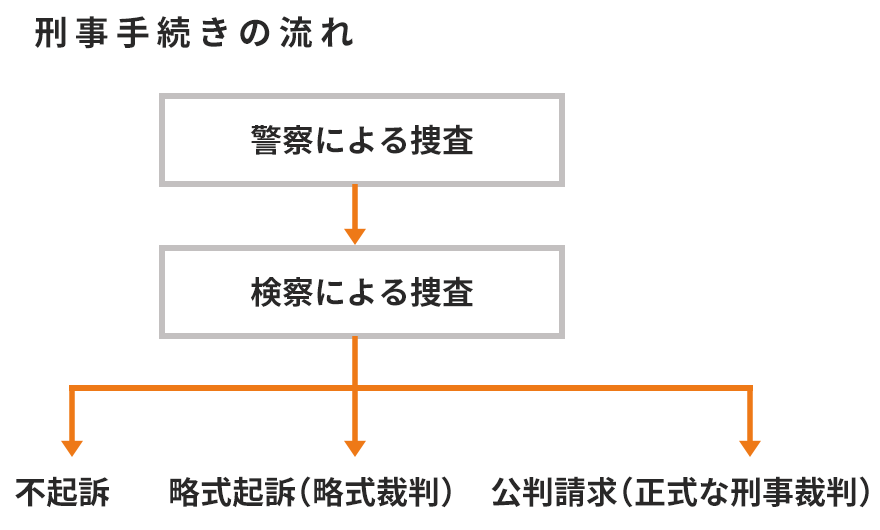
起訴は正式な刑事裁判と略式裁判の2種類
加害者が起訴されると、裁判手続きには「正式な刑事裁判(公判)」と「略式裁判」の2種類があります。どちらの手続きになるかは、事故の重大性や加害者の過失の程度などを踏まえて検察官が判断します。
① 正式な刑事裁判
検察官が加害者の罪を重いと判断し、正式な刑事裁判を行う場合は、地方裁判所で公判が開かれます。この裁判では、検察官が加害者の罪を立証し、被告人(加害者)や証人の証言、証拠などをもとに審理が進められます。
被害者も証人として呼ばれることがあり、法廷で証言を求められるケースもあります。裁判の結果、有罪となれば罰金刑や懲役刑が科されます。
② 略式裁判
比較的軽微な交通事故(人身事故でも軽傷の場合など)では、検察官が裁判所に「罰金刑での処分」を求め、裁判官が書面審理のみで罰金刑を決める場合があります。これを「略式起訴」といい、公判が開かれずに処分が決まります。この場合、被害者が裁判に関与することはありません。
不起訴で多い3つの理由
交通事故の刑事手続きでは、検察官が加害者を裁判にかけるか(起訴)、それとも裁判を行わずに終えるか(不起訴)を決めます。不起訴になると、加害者は刑事裁判を受けず、前科もつきません。
しかし、「加害者が罪を犯していないから不起訴になった」とは限りません。不起訴処分には、主に「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」の3つの理由があります。
① 起訴猶予
加害者の過失が認められ、法律上は罪に問える状態であっても、「あえて起訴しない」と判断されるケースです。これは、加害者に一定の反省や償いが見られる場合に適用されます。
具体的には、次のような事情などが考慮されます。
- 被害者との示談が成立し、被害回復がなされている
- 加害者が深く反省し、誠意をもって謝罪をしている
- 社会的制裁をすでに受けている
起訴猶予は、「加害者に責任がない」という判断ではなく、裁判にかけるほどの必要がないと考えられた場合に適用されます。そのため、たとえば、加害者の落ち度が大きい重大事故で、加害者が反省せず賠償もしないような場合には、起訴猶予となることは少ないです。
② 嫌疑不十分
「加害者が本当に罪を犯したのか、はっきりしない」と判断された場合、不起訴となります。交通事故は、証拠がはっきりしないことも多く、特に目撃者がいないケースなどでは、どちらの主張が正しいのか判断が難しくなります。
たとえば、次のような場合に嫌疑不十分となることがあります。
- 目撃証言がなく、事故の詳細が不明である
- 過失割合に争いがあり、加害者の責任が明確でない
- 被害者の証言と客観的な証拠が一致しない
このように、証拠が不足していると、検察官は「裁判で有罪にするのは難しい」と判断し、不起訴となることがあります。
③ 嫌疑なし
「そもそも加害者に違法性がない」「犯罪が成立しない」と判断された場合、不起訴処分となります。
具体的には、次のようなケースが考えられます。
- 加害者に明確な違法行為がない
- 事故そのものが不可抗力で発生した
- 被害者の過失が大きい
嫌疑なしの不起訴は、「加害者に責任がない」と明確に判断された場合に限られます。そのため、不起訴の中でも、被害者にとって納得しづらいケースといえます。
被害者としては、不起訴の理由を知ることが大切です。不服がある場合は、検察審査会に異議申し立てをすることも可能です。不起訴の判断に納得がいかない場合や、対応に困った場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
刑事裁判

加害者が正式に起訴されると、刑事裁判が開かれ、刑事罰が決定されます。刑事裁判は加害者の罪を明確にし、適切な処罰を下すための重要な手続きです。被害者としても、自分の被害や感情を伝え、加害者の責任を問うことができます。
刑事裁判の流れや注意点
交通事故で加害者が起訴されると、刑事裁判が行われます。刑事裁判には、正式裁判(公判)と略式裁判の2種類があります。
正式裁判の流れ
加害者の過失が大きい場合や、重傷・死亡事故の場合は、正式な刑事裁判が行われることが多いです。正式裁判の流れは次のとおりです。
-
第一回公判(初公判)裁判の冒頭で、裁判官が被告人(加害者)に対し、氏名や職業などの基本情報を確認します。その後、検察官が起訴状を読み上げ、加害者の罪状を明らかにします。最後に、加害者本人が、罪を認めるかどうか(認否)を問われます。
-
証拠調べ検察側が加害者の過失や違反行為を証明するために、事故の証拠や証人の証言を提出します。また被告人(加害者)自身も証言台に立って、事故態様や情状について述べることが一般的です。このとき、被害者が証人として出廷し、事故の影響や被害感情を述べることもあります。
-
弁論手続き検察官が、加害者にどのような刑罰を求めるのかを主張します。これを論告・求刑と言います。その後、加害者の弁護士が、減刑を求める弁論を行います。
-
判決判決では、裁判官が、加害者の罪を認定し、刑罰を決定します。有罪の場合、罰金刑・執行猶予付きの懲役刑・実刑判決などが下されます。
略式裁判
交通事故が軽微なものであるなどの理由により罰金刑が相当と判断された場合、略式裁判が適用されます。正式な法廷審理は行われず、簡易裁判所の裁判官が書類審理のみで判決を下します。
略式裁判の場合、被害者が裁判に参加することはありません。ただし、加害者に対する処罰が軽くなるため、「もっと重い処罰を求めたい」と考える場合は、検察官に正式裁判を求める意向を伝えましょう。
被害者参加制度の流れや注意点
被害者参加制度とは、交通事故の被害者や遺族が、刑事裁判に参加し、自らの意見を伝えることができる制度です。加害者がどのような刑罰を受けるのかに関わることができ、被害者の感情や意向を裁判官に直接伝えられます。
被害者参加制度の流れは、次の通りです。
-
被害者参加の申し出
交通事故で正式裁判となった場合、被害者は検察官に対して「被害者参加制度を利用したい」と申し出ることができます。申し出を受けた検察官は、裁判所に対して被害者の参加許可を申請します。裁判所が許可を出すと、被害者は正式に刑事裁判に参加できるようになります。
不起訴や略式裁判の場合被害者参加はできませんので注意が必要です。
被害者参加を希望する場合は、早めに申し出ることが大切です。裁判の進行によっては、申し出が遅れると手続きが間に合わなくなることがあります。
-
被害者参加の通知
検察官から、裁判の日程や手続きについての案内を受けます。被害者は、裁判の日程を確認し、参加する準備を整えます。
裁判では、被害者自身が発言する機会もあります。自分の意見を適切に伝えるため、どのようなことを話すかを事前に整理しておきましょう。
-
裁判に出席
被害者は裁判に出席し、裁判の進行を見守ることができます。傍聴人としてではなく、検察官の隣に座り、事件に関与する立場になります。
このとき、加害者と同じ法廷に立つことで、事故の詳細を思い出してしまう可能性があります。精神的な負担を考え、事前に弁護士や家族と相談し、冷静に対応できる準備をしておきましょう。
-
証人尋問や被告人質問
必要に応じて、証人や加害者(被告人)に質問をすることができます。「事故の経緯をもっと詳しく説明してほしい」「なぜ危険な運転をしたのか」など、加害者の態度や供述の真意を確かめることが可能です。
質問をする際は、感情的になりすぎず、冷静に伝えることが大切です。弁護士と相談し、質問の内容を事前に整理しておくと、スムーズに進められます。
-
意見陳述
被害者は裁判の中で、被害の実態や加害者への処罰感情を伝えることができます。
たとえば、「事故による精神的な苦しみ」「家族への影響」「加害者の反省が感じられないことへの不満」などを裁判官に直接伝えることが可能です。
裁判の時間には限りがあるため、短時間で伝えられるように準備しておくことが重要です。弁護士と相談しながら、簡潔に伝える内容を整理しておきましょう。
-
求刑意見の表明
被害者は、加害者にどのような刑罰を求めるのかについて、求刑意見を述べることができます。たとえば、「厳罰を望む」「執行猶予では納得できない」などの意見を伝えることが可能です。
求刑意見は裁判官の判断に影響を与えることがありますが、最終的な刑の重さは裁判所が決定します。そのため、感情的な発言だけでなく、事実に基づいた意見を述べることが大切です。
-
判決の確認
裁判の最終段階で、裁判官が判決を下します。被害者は、その判決を見届け、結果を確認します。
被害者の刑事手続きのポイント
被害者が刑事手続きに関与する際、次のポイントに留意することが重要です。
- 事故状況を記憶通りに正確に説明する
- 被害感情を警察や検察に適切に伝える
- 警察や検察の捜査に協力する
- 示談交渉は慎重に進める
- 悩んだら弁護士に相談する
① 事故状況を記憶通りに正確に説明する
交通事故の捜査では、被害者の証言が重要な証拠となります。事故直後は動揺して冷静に話すのが難しいかもしれませんが、できるだけ正確に状況を伝えることが求められます。事故の経緯を曖昧に話してしまうと、加害者側の言い分が優先され、被害者に不利な判断が下されることもあります。
事故当日のうちにメモを取る、事故現場や車両の写真を撮る、目撃者と連絡先を交換するなどして、できるだけ正確な情報を整理しておくことをおすすめします。
② 被害感情を警察や検察に適切に伝える
交通事故の被害者として、加害者の処罰を望むかどうかは、警察や検察の判断に影響を与えます。被害者の意向をしっかり伝えることが重要です。事故による肉体的・精神的な苦痛や日常生活への影響を明確に伝えましょう。
被害者の意見は、供述調書に記録され、検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な要素となります。特に、加害者が謝罪もせず反省の態度が見られない場合、その点を強調して伝えることで、厳罰を求める根拠になります。
③ 警察や検察の捜査に協力する
交通事故の刑事手続きでは、警察や検察の捜査に協力することが被害者に求められます。被害者の証言や提出する証拠が、加害者の責任を明確にするための重要な資料となるからです。
捜査に協力する場面としては、次のようなものがあります。
-
実況見分への立ち会い
事故現場で警察とともに事故の状況を再現し、どのように事故が発生したのかを説明します。
-
供述調書の作成
事故の経緯や被害状況を警察に詳しく話し、記録として残してもらいます。
-
検察官の取り調べ
検察官に事故の影響や加害者への処罰感情を伝え、起訴の判断材料にしてもらいます。
また、診断書や医療費の領収書、事故現場の写真や防犯カメラ映像、目撃者の証言など、証拠となる資料をできるだけ集めておくことも大切です。
捜査に積極的に協力することで、加害者の責任を明確にし、適正な処罰が下される可能性が高まります。
④ 示談交渉は慎重に進める
交通事故では、示談によって損害賠償の金額や支払い方法を決めることが一般的です。しかし、示談の内容によっては加害者の刑事処分に影響を与えることがあるため、慎重に進める必要があります。
示談を進める際の注意点は、次のとおりです。
- 加害者の求めに応じて安易に示談しない
- 賠償額が適正かを確認する
- 刑事処分への影響を考慮する
加害者の求めに応じて安易に示談しない
加害者側が「示談すれば処罰が軽くなる」と考え、早急に示談を求めてくることがあります。しかし、示談を急ぐことで、十分な賠償を受けられない可能性もあるため、焦らず慎重に交渉しましょう。
賠償額が適正かを確認する
治療費だけでなく、慰謝料、休業損害、後遺障害が残った場合の補償など、適正な損害賠償を受けられるかどうかを確認することが重要です。刑事処分への影響を考慮する
示談が成立すると、加害者が不起訴になる可能性が高まります。加害者に対して厳罰を求めたい場合は、示談を結ぶ前に慎重に判断しましょう。
示談交渉に不安がある場合は、弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。
⑤ 悩んだら弁護士に相談する
交通事故の刑事手続きは、加害者の処罰や示談交渉、被害者参加制度の活用など、被害者にとって判断が難しい場面が多くあります。特に、刑事手続きと民事手続き(示談交渉や損害賠償請求)が並行して進むケースもあるため、どのように対応すべきか迷うことも少なくありません。
弁護士に相談することで、交通事故の刑事手続き全般について適切なアドバイスを受けることができます。以下のようなメリットがあります。
示談交渉のサポート
刑事手続きが進む中で、加害者側の保険会社から示談を持ちかけられることがあります。しかし、示談の条件によっては、加害者の刑事処分に影響を与える可能性があるため、慎重に進める必要があります。
弁護士に相談すれば、適正な賠償額の確保と、刑事処分への影響を踏まえた示談交渉を進めることができます。
刑事手続きのサポート
被害者参加制度を利用する場合、どのような手続きが必要なのか、どのタイミングで意見を述べるべきかなど、弁護士のアドバイスが重要になります。
また、検察官とのやり取りや被害者意見陳述の準備についても、弁護士が適切なサポートを行います。
精神的な負担の軽減
交通事故の被害にあった方は、けがの治療や精神的なショックを抱えながら手続きを進めなければなりません。弁護士が介入することで、手続きの負担を軽減し、必要な場面で適切な対応ができるようサポートします。
刑事手続きの進行や示談交渉の判断に迷った場合は、弁護士に相談することで、納得のいく形で対応を進めることができます。交通事故の被害にあった際は、一人で抱え込まず、専門家の助けを借りることをおすすめします。
まとめ:刑事手続きの流れ
交通事故の刑事手続きは、「捜査→検察の判断(起訴・不起訴)→刑事裁判(起訴の場合)→判決」という流れで進みます。
被害者は、警察の捜査に協力し、事故の状況や被害感情を正しく伝えることが重要です。また、加害者の処罰に関与できる「被害者参加制度」を活用することもできます。
刑事手続きとは別に、示談交渉や損害賠償の話し合いも進みます。示談の内容によって加害者の処分に影響が出ることもあるため、慎重に進める必要があります。
交通事故の対応に不安がある場合は、弁護士に相談することで適切なサポートを受けられます。一人で抱え込まず、専門家と連携しながら、納得のいく解決を目指しましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博















