刑事手続きで意見を述べる方法
最終更新日:2025年03月19日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q刑事手続きで意見を述べたいときはどうすればよいですか?
-
捜査段階で意見を述べたいときは、次のような機会を利用しましょう。
- 供述調書の作成時
- 実況見分への立会時
- 警察に意見を述べる
- 検察官に意見を述べる
刑事裁判で意見を述べたいときは、⑤被害者参加や⑥心情に関する意見陳述を検討しましょう。
刑事裁判にならなかったことに不服で意見を述べたい場合、⑦検察審査会への申し立てを検討しましょう。

目次
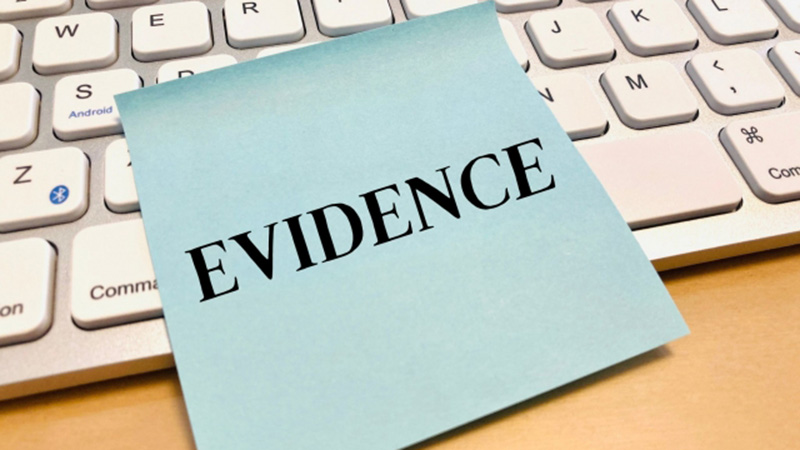
刑事手続きの流れ
刑事手続きは、①警察による捜査、②検察による捜査、③(起訴になった場合は)刑事裁判という流れで進みます。
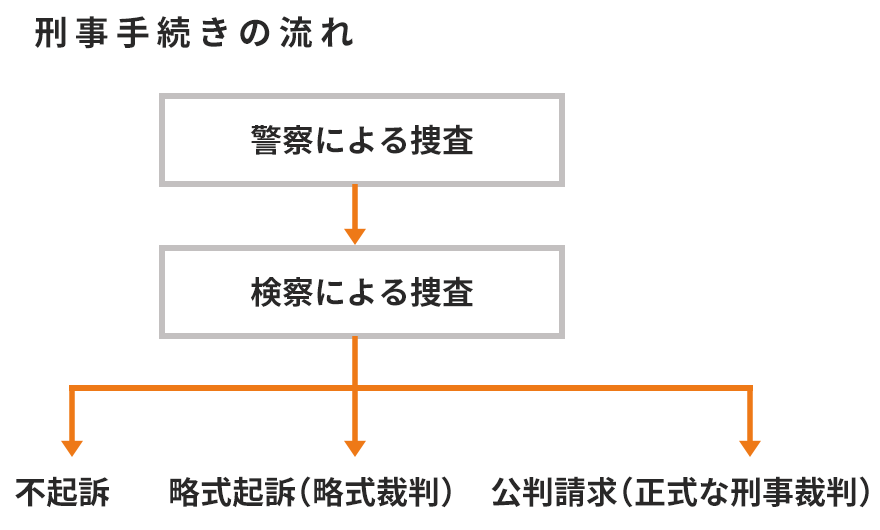
捜査段階
供述調書の作成
捜査段階では、事故の経緯や事故時の状況、加害者に対する処罰感情等について被害者への聞き取りがなされます。そして、供述調書が作成されます。
警察だけのこともありますし、警察と検察両方ですることもあります。
供述調書を作成するときは、内容の確認と署名押印を求められます。
内容に間違いがあるときは、安易に調書に署名・押印をしないことが大切です。
自身の記憶や主張と異なる点があれば、訂正や追加を申し立ててください。
特に、車両の速度や合図の有無、信号の色など過失割合に直結する事情については、慎重に内容を確認しましょう。
実況見分への立会
実況見分とは、事故現場において、警察官が当事者等から事故状況について聞き取りをして図面化・書面化するという現場検証作業です。
たとえば、いつ相手が視界に入ったのか、ブレーキを踏んだのはどの地点か、衝突した場所はどこか等について聞き取りが行われ、図面化・書面化されます。
けがをした事故では、加害者立会の実況見分調書は通常作成されます。しかし、被害者立会の実況見分調書は必ず作成されるわけではありません。
実況見分調書は、刑事裁判をはじめ、民事裁判や示談交渉においても、重要な証拠となるものです。しかし、加害者立会の実況見分調書しか作成されていないと、加害者の言い分を図面化した証拠しかないことになります。
そのため、事故態様に争いがある等の場合は、被害者立会の実況見分を求め、被害者の認識も図面化・書面化してもらうよう警察に伝えてみましょう。
警察に意見を述べる
供述調書の作成時や実況見分調書の作成時以外でも、被害者は、担当の警察官に対して事実上意見を述べることができます。
また、捜査に支障のない範囲で、捜査状況や加害者の言い分を教えてくれることもあります。
①加害者が謝罪しない、②保険会社の支払拒否(被害弁償がない)、③当初の見込みよりも症状や後遺障害が重くなった等の事情があるときは、積極的に警察に情報を提供しましょう。
被害者連絡制度
重大な交通事故事件等については、被害者連絡という制度があります。
重大な交通事故事件とは次の事件です。
- 死亡ひき逃げ事件
- ひき逃げ事件
- 死亡または全治3か月以上の傷害を負った事件
- 危険運転致死傷罪等に該当する事件
検察官に意見を述べる
事件が検察庁に送致された後、被害者は、担当の検察官に対しても事実上意見を述べることができます。
また、捜査に支障のない範囲で、捜査状況や処分の見通しを開示してくれることもあります。
被害者等通知制度
被害者は、検察庁に対し、加害者の処分結果を通知するように求めることができます。
通知を求めることができるのは、次のような情報です。
- 起訴不起訴等の処分結果
- (刑事裁判を行う場合は)裁判所及び裁判の日時
- 刑事裁判の結果
- (実刑になる場合は)収容される刑事施設
処分結果や警察の捜査記録は、過失割合に争いがあるときは非常に重要です。積極的に通知を希望しましょう。
不起訴処分に対し意見を述べる
検察審査会とは
加害者の起訴・不起訴は検察官が判断します。
もし検察官が不起訴という判断をして納得ができない場合、被害者は、検察審査会に審査を申し立てることができます。
検察審査会とは、不起訴という判断を、有権者からくじで選ばれた11人が審査する制度です。
申し立てがあった場合、検察審査会は、検察官がどのような事実上・法律上の判断に基づいて調べたのか、そこに見落としや誤りがなかったかを検討します。原則として書面審査ですが、担当検察官に対し、必要な資料を提出させたり、出席を求めたりすることもできますし、被害者も意見書や資料を提出することができます。
検察審査会の議決の種類
審査後には次のいずれかの議決をします。
- 起訴相当
- 不起訴不当
- 不起訴相当
① 起訴相当の議決
①起訴相当の議決とは、不起訴判断が不当であるだけでなく、積極的に起訴をすべきという議決です。
この議決がなされたときは、検察官は速やかに再検討をしたうえ、起訴または不起訴の処分をしなければなりません。
もし検察官が、再度不起訴処分をした場合には、検察審査会は再びこの処分の当否を審査します(第二段階の審査)。第二段階の審査で、やはり不起訴不当であり再度起訴議決の判断がなされると、裁判所が指定した弁護士が速やかに起訴を行い、強制的に刑事裁判が始まります。
② 不起訴不当の議決
②不起訴不当の議決とは、不起訴が不当であると判断する場合に行う議決です。
この議決がなされたときは、検察官は速やかに再検討をしたうえ、起訴または不起訴の処分をしなければなりません。
ただし①起訴相当の議決と異なり、再度検察官が不起訴としたとしても、その不起訴については第二段階の審査は行われません。
③不起訴相当の議決
③不起訴相当の議決は、検査官の不起訴判断が相当であるという判断です。これ以上の審査は行われません。刑事裁判
被害者参加
正式な刑事裁判になった場合、交通事故で死傷した被害者や遺族は刑事裁判に参加することができます。被害者参加と言います。(略式裁判の場合は、被害者参加をすることはできません。)
被害者参加をする場合、被害者は検察庁に申し出を行います。その後、検察官が裁判所に通知をし、裁判所が許可の決定をします。
被害者参加をすると、被害者は次のような活動ができます。
- 裁判への出席
- 検察官に対する意見を述べる
- 証人尋問
- 被告人質問
- 裁判所への意見陳述
① 裁判への出席
被害者は、裁判所や関係者と期日を調整したうえで、刑事裁判に出席できます。
この場合、傍聴席ではなく検察官席に着席できます。弁護士に依頼して、弁護士のみ出席することもできます。
加害者との関係で著しく不安や緊張をしてしまうときは、付添人や遮へいの措置が認められることもあります。
② 検察官に意見を述べる
被害者は、刑事裁判における刑事訴訟法上の検察官の全ての権限の行使に関し、意見を述べることができます。
被害者参加をする場合は、裁判期日の前に検察官と打ち合わせを行い、公訴事実や検察官の立証方針、尋問方針を確認します。そして、事故態様や被害感情の立証方針について不明点や意見がある場合、検察官に対し積極的に質問や意見を述べる必要があります。
③ 証人尋問
被害者は、証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、尋問をすることができます。ただし、尋問ができるのは情状に関する事項に限られます。
尋問をする場合、被害者は検察官にその旨を申し出、検察官が裁判所に通知をして、裁判所が決定をします。
加害者(被告人)は刑罰を軽くするために、家族や勤務先の関係者等を証人(情状証人)として呼んで、反省状況や再犯防止策を証言させることが多いです。これに対して、被害者は、情状証人の言っていることが本当かどうかを情状証人に質問できます。
④ 被告人質問
被害者は、被告人である加害者本人に対して質問できます。証人の場合と異なり、質問ができるのは情状に関する事項に限られません。
ただし、誘導や重複する質問が禁じられるなど、刑事訴訟法の一般的なルールには従わなければなりません。
質問を行う場合、被害者はあらかじめ検察官にその旨を申し出、検察官が裁判所に通知をして、裁判所が決定をします。
実務上は、検察官との質問事項の重複を避けるため、被害者が事前に質問内容を検察官に開示しておくことも多いです。質問を行うときは検察官や弁護士とよく相談しましょう。
⑤ 裁判所への意見陳述
被害者は、公訴事実に記載された事実の範囲内で事実または法律の適用について意見を述べることができます。刑罰について意見を述べることも可能です。
意見陳述を行う場合、被害者は予め検察官に意見の要旨を明らかにして申し出、検察官が裁判所に通知をして、裁判所が決定をします。
被害者は書面で意見の内容を準備し、検察官の意見陳述(論告求刑)のあとに書面を読み上げる方式で行うことが多いです。
心情に関する意見陳述
被害者参加制度とは別に、もう1つ裁判所に意見陳述を行う方法があります。被害感情や処罰感情などの情状に関する意見を陳述するもので、心情に関する意見陳述と呼ばれます。
方式は事実又は法律の適用に関する意見の陳述と同様ですが、犯罪の成否や法律の適用に関する意見は述べることができません。そのため、あらかじめ用意した文案を検察官が事前に確認することも多いです。
実際に被害者が刑事裁判に参加する場合、心情に関する意見と被害者参加制度上の事実又は法律の適用に関する意見の両方を陳述することが多いです。
まとめ:詳しい弁護士にまずは相談
刑事手続きの中では、被害者を置き去りしてはならないという精神の下、被害者が意見を述べたり、状況を知る方法が多く整備されています。
適切に刑事手続きに関わるなかで、真相が解明されたり、特に民事事件における過失割合に影響を与える例も多いです。また、被害感情や交通事故による影響をしっかりと伝えることで加害者の処罰に影響を与えることもあります。
捜査段階で少しでも疑問や意見がある場合は、警察や検察官に問い合わせることをおすすめします。
刑事裁判段階においても、被害者参加制度を使った様々な関わり方ができます。実際に参加をする被害者も増えている印象です。
よつば総合法律事務所では、刑事手続きにおける被害者側の弁護士としての活動も積極的に行っています。お困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博















