会社員男性が左足内側楔状骨骨折後の可動域制限(12級7号)、右尺骨骨折後の疼痛(14級9号)、左大腿内顆骨骨折後の疼痛(14級9号)で併合12級となり、1000万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月14日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博
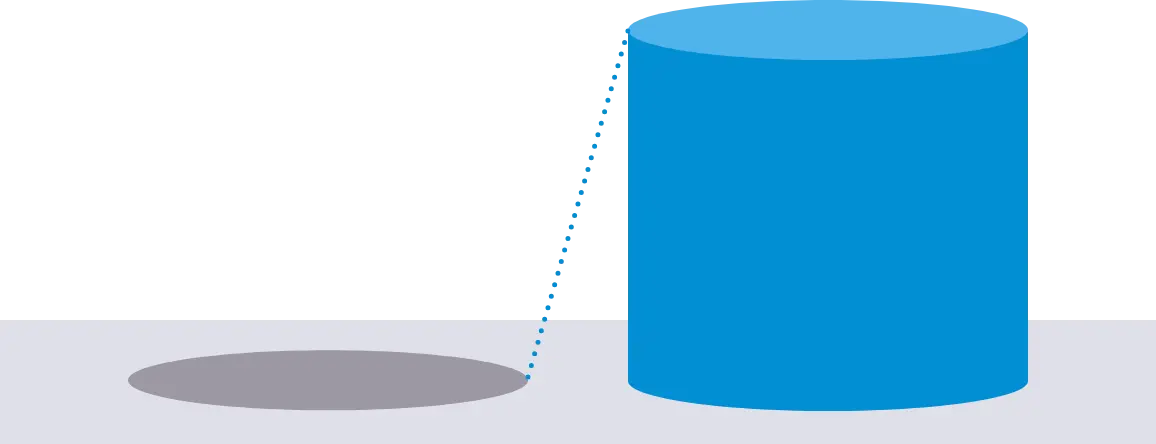
- 病名・被害
- 左足内側楔状骨骨折・右尺骨骨折・左大腿内顆骨骨折
- けがの場所
- 手・肩・肘足・股・膝
- 最終獲得金額
- 1000万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
田中さん(仮名)は車を運転していました。すると、反対車線を走っていた車がハンドル操作を誤り、センターラインオーバーとなります。田中さんは避けることもできず、相手の車と正面衝突しました。
ご相談内容
田中さんは次のけがをしました。重傷です。
- 左足内側楔状骨骨折
- 右尺骨骨折
- 左大腿内顆骨骨折
田中さんは今後の流れや後遺障害、今後の賠償のことなどが気になっていました。そこで、治療中に弁護士に相談します。
弁護士に頼んだ方がよいと考え、田中さんは治療中から弁護士に頼むことにしました。
田中さんのご相談内容のまとめ
- 治療中だが今後の流れが気になっている。
- 後遺障害のことが気になっている。
- 今後の賠償のことが気になっている。

弁護士の対応と結果
治療中に弁護士は代理しました。そして、休業損害の交渉から弁護士はスタートします。
田中さんの仕事は立ち仕事であり、職場になかなか復帰できませんでした。そこで、弁護士が代理して休業損害の請求をしたり、復職の時期を調整したりしました。その結果、スムーズに休業損害をもらうことができました。
その後、事故から1年間ほど田中さんは治療を続けます。しかし、特に左足の痛みや動きの制限などが改善せずに症状固定となりました。
弁護士がサポートをして後遺障害の申請を田中さんは行います。その結果、後遺障害は次の通り12級となりました。
- 左足内側楔状骨の骨折後の動く範囲の制限について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)
- 右尺骨骨折後の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 左大腿内顆骨の骨折後の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合12級
自賠責保険に請求をして後遺障害となると、自賠責保険会社から先に保険金がもらえます。田中さんは12級になったので、先に224万円をもらえました。
その後、弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。逸失利益が大きな争いとなったものの、弁護士は田中さんの主張を大きく認めさせることに成功しました。その結果、任意保険会社から1000万円をもらうことができました。
田中さんは合計で1224万円を受領することができました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 後遺障害の申請をした。
- 併合12級の後遺障害を獲得した。
- 自賠責保険461万円、任意保険420万円の合計881万円を獲得した。
解決のポイント
1. 休業損害全額の獲得
休業損害とは事故により仕事を休んだ損害です。
田中さんには左足の痛みや動く範囲の制限がありました。田中さんの仕事は立ち仕事であるため、職場になかなか復帰できないという状況が続いていました。
休業損害の毎月の支払いを打ち切りたいと、保険会社は治療中に通告してきました。しかし、弁護士が代理して、被害者の症状や勤務先との話し合いの状況を伝え、粘り強く交渉を続けました。
その結果、休業期間の全期間について保険会社は支払いをしました。
2. 減額分の賞与の獲得
田中さんは、長期にわたる休業のため賞与が減ってしまいました。そこで、賞与減額証明書の作成を職場に依頼しました。そのうえで、保険会社に資料を送付したところ、減額分全額の賞与を保険会社は支払いました。
3. 逸失利益の大幅な増額に成功
逸失利益とは、後遺障害になったことにより発生する今後の収入減への賠償です。
今後の収入が減る期間について、田中さんは67歳までの20年を主張していました。他方、保険会社は10年を主張していました。
弁護士が交渉を続けたところ、67歳までの20年間収入が減ることを前提とする合意ができました。その結果、逸失利益が大幅に増えました。
ご依頼者様の感想
2年間にわたりお世話になりました。本当にありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q賞与の減額は賠償の対象になりますか?
-
事故による減額と証明できれば賠償の対象になります。職場に賞与減額証明書を作成してもらいましょう。
「なぜ賞与が減額になったのか」という具体的な計算式があると請求が認められやすくなります。
- Q逸失利益の期間は何年が基準ですか?
-
症状固定から67歳までの期間が基準となることが多いです。たとえば、40歳で症状固定だと、67歳までの27年間です。
もっとも、例外もあります。悩んだら交通事故に詳しい弁護士にまずは相談することをおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博















