会社員が母指中手骨骨折後の母指の機能障害(10級7号)となり、2100万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月10日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 今村 公治
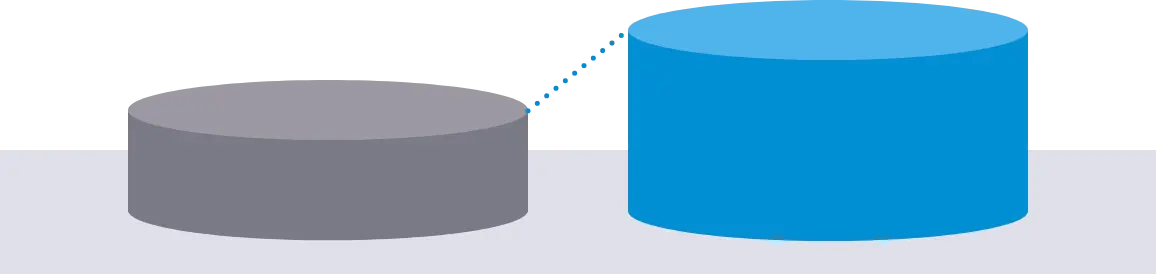
- 病名・被害
- 右母指中手骨骨折
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 2100万円
- 後遺障害等級
- 10級
事故の状況
畑山さん(仮名)はバイクに乗ってT字路にさしかかりました。畑山さんは直進です。すると、右から突然車が出てきました。畑山さんはよけることができず、車とぶつかりました。
木本さんは、右母指中手骨骨折のけがをしました。右手の親指の骨折です。
ご相談内容
木本さんは右母指中手骨骨折のけがをします。9カ月ほど治療を続けました。しかし、治らずに症状固定となります。木本さんには右手の親指が十分に曲がらなかったり、親指に力を入れたり曲げたりすると痛みが出たりという症状が残ってしまいました。
木本さんの後遺障害は「一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの」(10級7号)となりました。
その後、木本さんは保険会社から賠償金の案を受け取ります。金額は約1100万円でした。木本さんは1100万円が妥当かどうかよくわかりません。そこで、木本さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをしました。
木本さんは弁護士と面談をします。木本さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
- 1100万円は少ない。
- 裁判の基準だと2000万円以上になる可能性が高い。
木本さんは弁護士に依頼した方がよいと考えて、弁護士に頼むことにしました。

弁護士の対応と結果
既に木本さんは後遺障害10級7号となっていました。そこで、10級7号を前提に、弁護士は加害者の任意保険会社との交渉をすぐにスタートします。慰謝料や逸失利益が争いとなったものの、2100万円を受け取る合意がまとまりました。
1100万円から2100万円に増えましたので、約1.9倍となりました。解決までは約4カ月です。
解決のポイント
1. 入通院慰謝料の増額
入通院慰謝料とは入院や通院をしたことへの慰謝料です。入院期間や通院期間により決まってきます。
慰謝料には3つの基準があります。次の3つです。
- 自賠責保険の基準
- 任意保険の基準
- 裁判の基準
①自賠責保険の基準が一番低く、③裁判の基準が一番多いことが多いです。
今回は、弁護士は裁判の基準に基づいて請求をしました。その結果、ほぼ裁判の基準に基づく解決となりました。
2. 後遺障害慰謝料の増額
後遺障害慰謝料とは、後遺障害になったことへの慰謝料です。後遺障害の等級などにより決まってきます。
後遺障害10級の裁判の基準の慰謝料は420万円です。
今回は、弁護士は裁判の基準で請求をしました。その結果、裁判の基準である420万円をもらうことができました。
3. 逸失利益の増額
逸失利益とは、後遺障害による今後の収入減への賠償です。事故前の年収や後遺障害の等級、何年位影響があるかという期間などにより決まってきます。
今回は、保険会社が提示する逸失利益は少ないものでした。具体的には、逸失利益の期間である労働能力喪失期間が短いものでした。
裁判の基準だと、労働能力喪失期間は症状固定から67歳までのことが多いです。弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、期間を67歳までとする合意がまとまりました。そのため、逸失利益の金額が300万円以上増えました。
ご依頼者様の感想
どうもありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q慰謝料の増額のポイントは何ですか?
-
裁判の基準に基づく金額を主張しましょう。また、弁護士費用特約があるときは弁護士に相談や依頼をしましょう。弁護士が代理するだけでも慰謝料が増えることがあります。
- Q逸失利益の増額のポイントは何ですか?
-
次の点を検討しましょう。
- 後遺障害の等級
後遺障害の等級が変われば逸失利益の金額も変わります。後遺障害の異議申し立ても検討しましょう。
- 事故前の年収
事故前の年収により金額が変わります。自営業などで年収が争いになることもあります。適切な証拠に基づく年収を主張しましょう。
- 労働能力喪失期間
事故の影響がある期間により金額が変わります。労働能力喪失期間といいます。症状固定から67歳までのことが多いですが、後遺障害の内容や被害者の年齢により変わります。
悩んだら、交通事故に詳しい弁護士にまずは相談しましょう。
- 後遺障害の等級

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 今村 公治















