腓骨遠位端開放骨折や脛骨遠位端開放骨折、アキレス腱断裂により併合12級となった事例
最終更新日:2023年03月02日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎
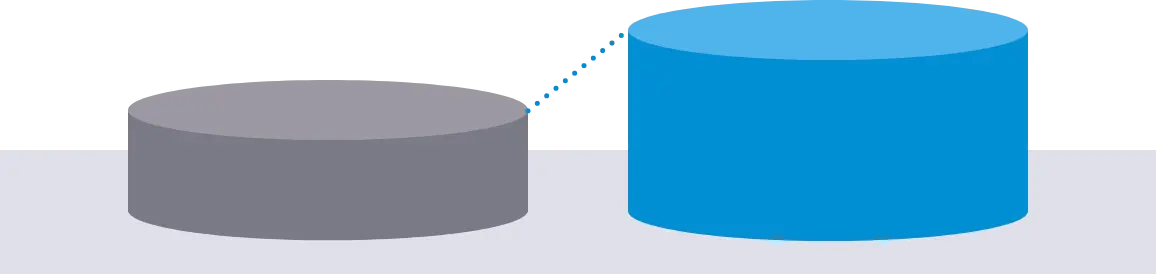
- 病名・被害
- 腓骨遠位端開放骨折・脛骨遠位端開放骨折・アキレス腱断裂
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 967万円
- 後遺障害等級
- 12級14級
事故の状況
土門さん(仮名)はバスに乗っていました。すると、バスが運転を誤り、ガードレールにぶつかりました。
土門さんはバス内で転んでしまい、右腓骨遠位端開放骨折や右脛骨遠位端開放骨折、左アキレス腱断裂のけがをしました。
ご相談内容
土門さんは、腓骨遠位端開放骨折や脛骨遠位端開放骨折、アキレス腱断裂のけがをします
入院と通院による治療を4年も続けました。しかし、完治することなく症状固定となりました。
そして、後遺障害は次の通りとなりました。
- 右足関節の可動域制限について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)
- 左足のアキレス腱の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合12級
後遺障害12級になったあと、土門さんはよつば総合法律事務所の弁護士に相談をします。後遺障害の等級が適切かどうか土門さんは気になっていました。また、今後の賠償金のことも気になっていました。弁護士費用特約もあったため、土門さんは弁護士に頼むことにしました。
土門さんのご相談内容のまとめ
- 12級の後遺障害が適切がどうか気になる。
- 賠償金のことが気になる。

弁護士の対応と結果
まずは12級の後遺障害が妥当かどうか弁護士は検証します。具体的には、10~11級を目指す異議申立ができないかどうか検討しました。
可動域制限の程度や画像所見などからすると、異議申立をしても結果が変わらない可能性が高い状況でした。そのため、今回は異議申立はしないことにしました。
その後、弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
保険会社の提示額は613万円でした。しかし、金額が少なかったため弁護士は交渉を続けます。そして、交渉のみでは解決できなかったため、交通事故紛争処理センターへの申立も弁護士はしました。
紛争処理センターでは1回目の期日で合意しました。金額は967万1773円です。はじめの提示額613万円から1.6倍に増額しました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 弁護士が代理して増額を交渉した。
- 交通事故紛争処理センターに申立をした。
- 賠償額が約613万円から約967万円と1.6倍に増額した。
解決のポイント
1. 紛争処理センターへの申立
土門さんは、過度の負担がかからない早期の解決を希望していました。
保険会社との交渉方法には次の3つがあります。
- 直接の交渉
- 交通事故紛争処理センターへの申立
- 民事裁判の提起
③民事裁判を起こすと、今まで問題になっていなかった争点が発生したり、1~2年の期間が解決までにかかってしまったりすることもあります。
今回は、土門さんの要望を踏まえて、②交通事故紛争処理センターへの申立をすることにしました。2カ月ほどの期間で解決できて、賠償額も増えました。
2. 裁判基準による逸失利益の獲得
逸失利益とは、後遺障害により減少する将来の収入の賠償です。
紛争処理センターでは、裁判の基準と同じ基準でのあっせんとなるのが原則です。土門さんも、裁判の基準と同じ、次のような計算での逸失利益を獲得できました。
3. 裁判基準による慰謝料の獲得
紛争処理センターでは裁判の基準と同じ基準でのあっせんとなるのが原則です。土門さんも、裁判の基準と同じ次のような慰謝料を獲得できました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。私はお店をやっていますので、今度近くにくることがありましたらぜひお立ち寄りください。
(茨城県取手市・60代・女性・無職)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q交通事故紛争処理センターとは何ですか?
-
交通事故紛争処理センターとは、交通事故被害者の中立・公正かつ迅速な救済を図るため、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん及び審査業務を無償で行う公益財団法人です。
交通事故紛争処理センターに和解あっせん申立をすると、受領できる保険金が増額することが多いです。解決までの期間は3~6カ月が目安です。
- Q逸失利益の期間が平均余命の半分となるのはどのようなときですか?
-
50代以上のときは平均余命の半分となるときがあります。67歳以上のときは平均余命の半分になります。
被害者の状況 労働能力喪失期間 通常の場合 67歳までの年数 18歳未満の子供 49年(18歳から67歳まで) 大学生 大学卒常から67歳までの年数 67歳までの期間が短い場合 「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1の年数」のうち長い年数 67歳を超えている場合 平均余命の2分の1の年数 むちうちの場合 14級は5年程度
12級は10年程度注 個別事案によります。
平均余命は簡易生命表(厚生労働省)を利用することが多いです。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎















