右手関節の可動域制限で12級6号となり1100万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月02日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎
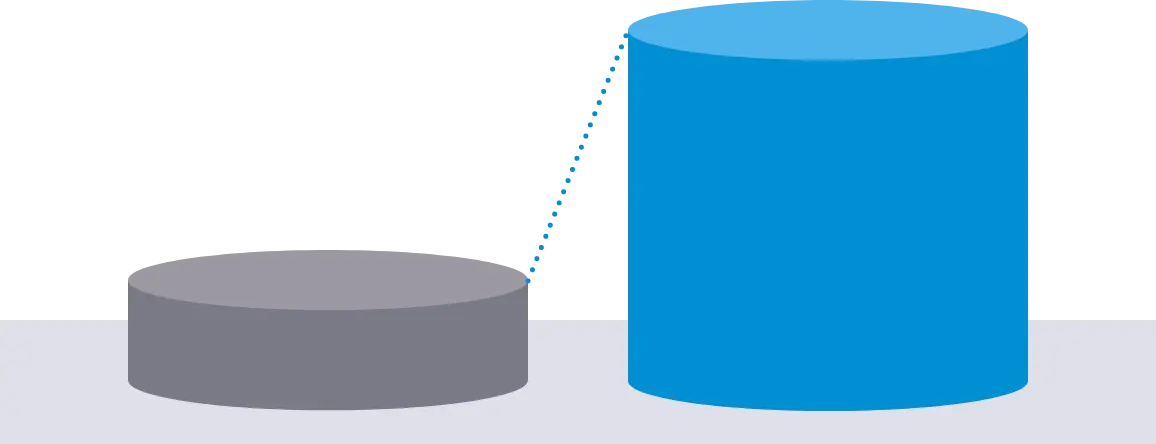
- 病名・被害
- 右橈骨遠位端骨折・右尺骨茎状突起骨折
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 1082万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
鈴木さん(仮名)はバイクを運転していました。鈴木さんがまっすぐ進んでいたところ、対向車線から車が近づいてきます。車は突然右折しました。
鈴木さんは避けようとしますが避けられませんでした。鈴木さんは、右橈骨遠位端骨折、右尺骨茎状突起骨折のけがをしました。
ご相談内容
鈴木さんは、橈骨遠位端骨折や尺骨茎状突起骨折のけがをします。右手の関節の痛みや可動域制限に悩みます。
約1年間病院でリハビリをしましたが、完全には治りませんでした。
鈴木さんの後遺障害は「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)となります。保険会社は鈴木さんに426万5768円の示談金を提案しました。
鈴木さんは今後どのようにすればよいかよくわからなかったため、よつば総合法律事務所に問い合わせをしました。
鈴木さんと弁護士が相談をしたところ、次のことがわかりました。
- 保険会社の提案額約430万円は低すぎること
- 弁護士が代理すれば1000万円を超える保険金になることもありえること
鈴木さんは弁護士に頼むのがよいと考え、弁護士に頼むことにしました。
鈴木さんのご相談内容のまとめ
- 保険会社の提案430万円が適切かどうかわからない。
- 保険金が増えるのであれば増やしたい。

弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。鈴木さんは事故時に無職でした。そのため、休業損害や逸失利益が争いとなりました。また、けががいつころ治るのかということも争いになったため、労働能力喪失期間も協議が必要となりました。
弁護士が交渉を続けた結果、最終的には1082万9025円を受け取る合意がまとまりました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 弁護士が代理して保険金の増額を交渉
- 賠償額が約430万円から1080万円と2.5倍に増額
解決のポイント
1. 失業中の休業損害の獲得
鈴木さんは事故時にたまたま失業中でした。そのため、保険会社は失業中のため休業損害はゼロと主張していました。
しかし、労働能力と労働意欲があり、就労の可能性が高いときは、失業者でも休業損害の請求ができます。
弁護士が交渉を続けたところ、事故の被害のせいで就職が遅れたとして、4か月分の休業損害を認めさせることができました。
2. 無職者の逸失利益の獲得
逸失利益とは将来の収入減への賠償です。鈴木さんは事故時は無職でした。そのため、どれだけ将来の収入減が発生するかはっきりしませんでした。
そこで、弁護士は次の資料をそろえて交渉をしました。
- 鈴木さんが仕事をしていたころの年収の資料
- 40代男性の平均的な年収の資料
最終的にはある程度は満足いく逸失利益を獲得することができました。
3. 67歳までの期間の逸失利益を獲得
保険会社は、労働能力喪失期間を8年として逸失利益を算定していました。
しかし、労働能力喪失期間は、症状固定の日から原則として67歳までです。そして、弁護士が交渉をした結果、労働能力喪失期間は症状固定日から67歳までの約20年とすることができました。
逸失利益の金額も約330万円から約640万円まで引き上げることができました。
ご依頼者様の感想
納得のいく金額での解決ができました。ありがとうございました。
(千葉県野田市・40代・男性・無職)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q橈骨遠位端骨折はどのような後遺障害となることが多いですか?
-
次の後遺障害となることが多いです。
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q尺骨茎状突起骨折はどのような後遺障害となることが多いですか?
-
次の後遺障害となることが多いです。
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q失業中でも休業損害はもらえますか?
-
労働能力と労働意欲があり、就労の可能性が高いときはもらえます。たとえば、既に内定を得ていて勤務開始日が決まっているようなときは、休業損害が認められるでしょう。
- Q逸失利益の就労可能年数はどのように決まりますか?
-
症状固定日から67歳までの期間が多いです。ただし、例外もあります。
被害者の状況 労働能力喪失期間 通常の場合 67歳までの年数 18歳未満の子供 49年(18歳から67歳まで) 大学生 大学卒常から67歳までの年数 67歳までの期間が短い場合 「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1の年数」のうち長い年数 67歳を超えている場合 平均余命の2分の1の年数 むちうちの場合 14級は5年程度
12級は10年程度注 個別事案によります。
平均余命は簡易生命表(厚生労働省)を利用することが多いです。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎















