股関節脱臼骨折(12級)にて1348万円を獲得した、千葉県柏市の30代の会社員の事例
最終更新日:2024年10月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎
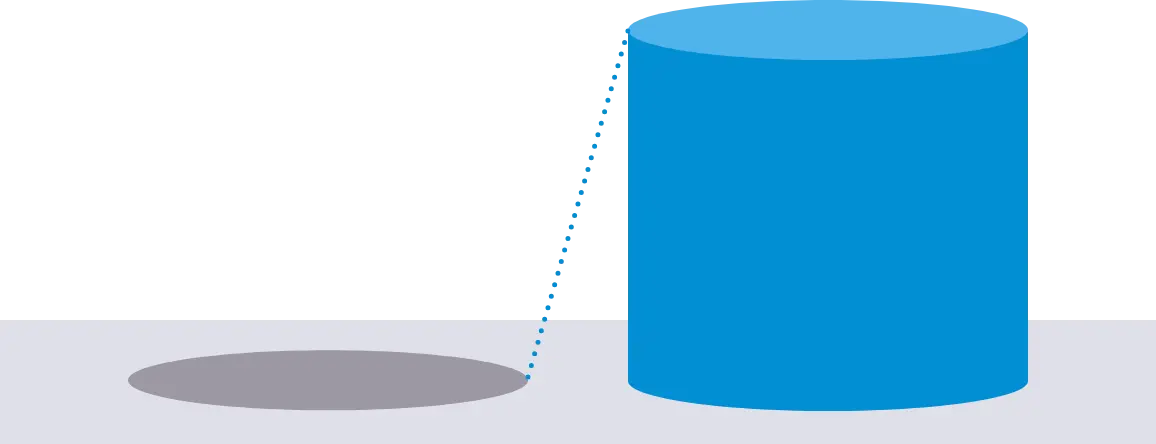
- 病名・被害
- 股関節脱臼骨折・腸骨骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 1348万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
事故現場は信号のある十字路です。江川さん(仮名)が自動車に同乗して、交差点を進んでいたところ、右折対向車に衝突されました。
ご相談内容
江川さんのけがは股関節脱臼骨折と腸骨骨折の重傷です。
事故後2か月で弁護士に相談
江川さんは1か月半ほど入院したあとに退院します。
退院したあとに江川さんは弁護士に相談します。今後の治療費のこと、後遺障害のこと、賠償金のことなどが心配だったからです。今後の流れのこともよくわかりませんでした。
費用の心配もなかったので弁護士に依頼
江川さんは弁護士費用特約に入っていました。そのため、弁護士に頼んでも弁護士費用の自己負担は原則ありません。
費用のことが江川さんは心配でした。もっとも、弁護士費用特約で大丈夫ということだったので、江川さんは弁護士に頼むことにしました。

弁護士の対応と結果
江川さんは事故から6か月の通院を続けます。しかし、症状は完治せずに症状固定となります。
後遺障害は12級7号を獲得
事故から2か月の段階で弁護士は依頼を受けていました。そのため、実況見分調書などの刑事記録やカルテの取り寄せがスムーズに進んでいました。後遺障害が江川さんの職業に与える影響をまとめた書面も作成しました。
後遺障害診断書などの書類もそろえて、弁護士は後遺障害の申請をします。
その結果、股関節の動く範囲の制限について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)となりました。
自賠責保険会社から448万円を獲得
自賠責保険に申請をして後遺障害となると、先に自賠責保険から保険金をもらえます。
今回は、江川さんが乗っていた車両とぶつかってきた加害車両の2つの自賠責保険に弁護士は請求をしました。
そのため、それぞれ224万円を自賠責保険会社から江川さんはもらうことができました。合計で448万円です。
任意保険会社から900万円を獲得
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
比較的交渉はスムーズに進みます。約2か月の交渉期間で900万円を獲得することができました。
江川さんが受け取った金額のまとめ
| 自賠責保険(運転者) | 224万円 |
|---|---|
| 自賠責保険(加害者) | 224万円 |
| 任意保険(加害者) | 900万円 |
| 合計 | 1348万円 |
解決のポイント
1. 後遺障害の請求の添付資料を準備
後遺障害の請求のときに、弁護士は次の準備をしました。
- 実況見分調書などの刑事記録で衝撃の程度の強さを証明
- カルテなどで症状の一貫性を証明
- 後遺障害が仕事に与える影響をまとめた書面を作成
- 後遺障害診断書の作成方法をアドバイス
その結果、江川さんも納得できる12級7号の後遺障害となりました。
ご依頼者様の感想
本当にありがとうございました。大変満足しています。
(千葉県柏市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q股関節骨折ではどのような後遺障害になりますか?
-
障害の種類や程度に応じて、次の後遺障害になることがあります。
- 可動域制限の機能障害
- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級7号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 痛み
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 人工骨頭置換術又は人工関節置換術を行った場合
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 変形障害
- 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの(10級8号)
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(12級5号)
- 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの(13級8号)
- 可動域制限の機能障害
- Q「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)と「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)は同じ12級です。同じ12級でも認定された内容の違いにより損害賠償の交渉に与える影響はありますか?
-
あります。特に、逸失利益に影響を与えることがあります。
12級13号は逸失利益の労働能力喪失期間を10年程度に限定することが多いです。一方、12級7号は症状固定時から67歳までの期間すべてにすることが多いです。たとえば、30歳で症状固定のときは37年です。
そのため、12級7号の方が賠償額が多くなる傾向にあります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎















