会社員が14級9号の認定を受け、3か月という短い交渉で200万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子
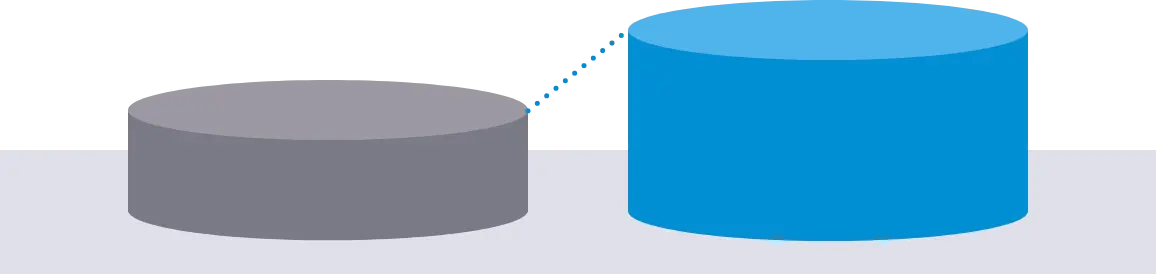
- 病名・被害
- 頸椎捻挫・肘部管症候群
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 200万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
会社員の菅原さん(仮名)はバイクを運転中、信号のない交差点で自動車と衝突するという事故にあいました。バイクは倒れ、菅原さんは右ひじなどを強く打ってしまいました。
菅原さんは首や右ひじにケガを負い、痛みなどの症状が出ました。
ご相談内容
菅原さんのケガは頚椎捻挫と右肘部管症候群でした。菅原さんは病院で治療を受けましたが、ケガは完全には治りきらずに症状固定となりました。
後遺障害が残ったこともあり、きちんと賠償を受けたいと思った菅原さんは、後遺障害認定の後によつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。
菅原さんのご相談内容のまとめ
- ケガと過失割合にみあった金額の賠償を受けたい/li>
- とにかく早めに解決してほしい
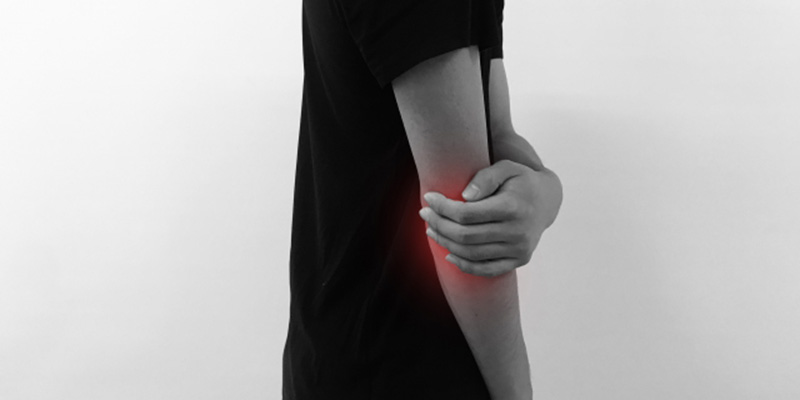
弁護士の対応と結果
菅原さんの相談をうけたよつば総合法律事務所の弁護士は、入通院慰謝料について、より金額が高くなる算定表を使うべきだと主張しました。これにより、高い金額の算定表を使うことが認められ、入通院慰謝料が増えました。
また、過失割合と逸失利益の期間についても菅原さんとよく検討し、早めに解決したいというご希望に沿う形での解決を目指しました。
その結果、3か月という短い期間で交渉を成立させることができました。また、賠償額は約200万円になりました。
保険会社の最初の提示金額が103万円だったので、約97万円も増えたことになります。過失割合は、菅原様25%、相手方75%でした。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 入通院慰謝料の算定表について適切な主張をして、慰謝料の金額が上がった
- 菅原様の希望をきいて、逸失利益について合理的な主張を行い、早い解決につながった
解決のポイント
1. 入通院慰謝料の算定表を主張どおり認めさせた
入通院慰謝料は、「赤い本」という本に載っている算定表に基づいて計算されます。この算定表には別表Ⅰと別表Ⅱの2種類があります。
- 別表Ⅰ
骨折など重いケガの場合に使われる算定表
- 別表Ⅱ
画像所見がない、むちうち症や打撲、ねんざなど比較的軽いケガの場合に使われる算定表
ケガがひどければ別表Ⅰで算定して高い金額の入通院慰謝料がもらえます。一方で、ケガが軽ければ別表Ⅱで算定した比較的安い慰謝料をもらうことになります。
菅原さんのケガは頚椎捻挫と右肘部管症候群だったため、別表Ⅱが使われてもおかしくないケースでした。しかし、よつば総合法律事務所の弁護士は、単なるむちうちの14級とは違うという事情を主張しました。
その結果、別表Ⅰで計算した慰謝料の満額を認めさせることができました。
2. 早く解決するために無理筋の主張はさけて合理的な金額で和解した
逸失利益を算定するための労働能力喪失期間について、はじめは67歳までを主張していました。
しかし、早く解決したいという菅原さんのご意向が強かったこと、実務では14級9号の場合は労働能力喪失期間が5年に限定されるケースが多いことを踏まえて、菅原さんと話合い、5年で合意することにしました。
ただし、同じ14級でも可動域制限などがある場合には、容易に5年で合意せずに67歳までの労働能力喪失期間を主張したほうがよいと考えます。
3. 人身傷害保険の利用の検討
過失割合が菅原様25%、相手方75%になることを予測していました。そのためよつば総合法律事務所の弁護士は、25%分については菅原様が加入していた人身傷害保険への請求を考えていました。
しかし、残念なことに人身傷害保険の対象となる事故ではないことが判明したため、請求は行いませんでした。
今回のケースでは使えなかったのですが、人身傷害保険が使える事故もあります。被害者にも過失がある場合には、人身傷害保険の利用を検討し、十分な補償が得られるように進める必要があります。
ご依頼者様の感想
比較的早く終わり、裁判にもならずによかったです。
(千葉県柏市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q人身傷害保険とはどういった保険ですか
-
交通事故によってケガをしたり死亡したりしたときに、自分の過失割合に関係なく保険金の支払いを受けられる保険です。
- Q交渉の場合に過失割合はどのようにして判断するのですか?
-
交通事故の過失割合については、通称「緑本」と呼ばれる本に書かれた内容が裁判上の基準となります。交渉においてもまずは緑本を基礎にして相手方と主張を出し合い、合意できる割合を探っていくことになります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 佐和子















